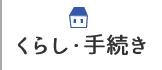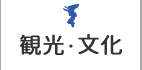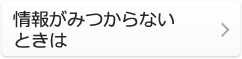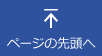三人姉弟で逃げまどう:竹宮 悦子
最終更新日:2016年4月1日
徳島市南矢三町 竹宮 悦子
「警戒警報」が出た。まだ宵の口、父は「子どもとばあさんは防空壕へ先に行っとれ。」と言う。今夜も大したことはないと踏んだ父の考えだった。毎日、何度も繰り返される警戒警報、空襲警報への慣れから来るのかも知れない。
両親の故郷徳島へ大阪から引っ越してきてまだ一ヶ月弱。伊月町から富田国民学校へ行く道さえ、うろ覚え状態だ。その上、夜は敵機にねらわれるため、消灯は常識だった。暗闇のため道順がわからず、ばあさんの後に付いて子ども三人は町内の防空壕へ急いだ。防空壕の中は暗闇で何も見えない。ばあさんがどこにいるのかもわからず、三人は奥へ押し込まれた。近所の人も来ていたようだ。土の上に座った。静かだった。子どもの寝る時間と暗闇に、いつのまにか三人は眠った。私が九歳、弟は七歳と五歳だ。
「爆弾が落ちたぞ。早く逃げろ。」
大声で叫んでも寝入り端の子どもには無理な話。何度目に目が覚めたんだろう。呼び起こされたときは、防空壕の中から全員逃げ出し、ばあさんもいなかった。防空壕から引き出された三人は、我が家に向かうその先を両手でふさがれ、
「こっちは行けんぞ。あっちへ逃げろ。」
とおじさんは指さした。どっちの道も両側の家はすでに火の海になっていた。仕方なく命令されるままあっちの道へ走った。火の玉になった家の前を一人ずつ走り抜けた。三人は手をつないで大勢の人の後に付いて走った。
「ねえちゃん、こいつを真ん中にせな走れんわ。」
無言のまま五歳の弟を真ん中にした。小川の中には大勢の人が首まで水に入っていた。怖くてその場を逃げた。行き交う人も走った。黒い倉を回ると、火の海は三人に覆いかぶさってきた。遊廓の中だった。引き返す弟の頭巾に火の粉が降った。
「ちょっと待ち、頭巾に火がついとる。」
と大声を上げながら払ってくれたおばさん。綿に火がつくと魔物のように広がるとばあさんから聞いていた。怖くて足がすくんだ。また懸命に走った。気が付くと前を走る人は一人もいなくなっていた。暗闇に回りの木々が真っ黒のお化けのように三人をふさいだ。必死であたりを見回した。木の間に入口があった。
「姉ちゃんこわいよ。」
「どうしよう。」
「この中に入ろう。」
三人はそろっと入っていった。富田の明神社だった。
「お助けください、とお祈りをしよう。」
三人はお手洗い水を頭巾に掛け合い、祈った。
「どうする、こっちから出て行こうか。」
暗闇の静かな神社の中は、得も知れぬ恐怖感に襲われ、いたたまれなかった。神社の裏は本物のお化けが出てくるように思った。
「こっち行こうか。」
あたりはまだ暗かった。少し歩くと横土手に出た。三人は横土手の真ん中あたりに立った。目の前の田んぼの真ん中に、黒い人型のものが、うごめいていた。
「そこの子ども、伏せろ。」
土手の下から大きな声で怒鳴る男の声がした。三人はその声が終わらぬ内に土手の下へ飛び降りた。その瞬間、頭の上を焼夷弾が轟音と共に通過した。
「よかったな。」
と若い夫婦の笑顔があった。まだお礼を言うすべを知らなかった。どこのどなたか今もってわからないが、大人になって命の恩人であることを知る。夜通し走った三人は、土手の下が気持ちよくいつの間にか寝てしまった。
「姉ちゃん、あれ父ちゃんと母ちゃんと違うか。」
寝ていた私を揺り起こした。タオルを頭に巻き、母と乳母車を押し土手を上がってくる姿は、自分の知ってる両親とどう見ても違っていた。
「違うよ。」と冷たく言った。
「絶対そうだよ。」
懸命に訴える弟に仕方なく考えた手段は、
「聞いてきたら。」と、弟をその夫婦の所へ行かせた。
「姉ちゃん、そうだったよ。」と、弟は息せききって走って帰った。
三人は両親の元へ走った。
「よう生きとった。よう生きとった。」と、両手に弟を抱きしめ、泣き崩れる母の姿を見ていた。父はその情景を眺めたまま突っ立っていた。一体この人達は誰だろう。何をしてるのだろう。本当に長い間、会わなかった人達だ。信じられなかった。今は何時だろう。
このページに対する連絡先
総務課 文書担当
電話:088-621-5017
FAX:088-654-2116
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。